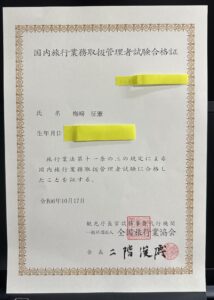6月18日は昨年亡くなった僕の妹の一周忌だった。
一年前の葬儀の事を今も僕ははっきりと覚えている。
通夜の晩には幾度となくもう目を開ける事のない妹の顔を見つめ、落涙した事だろうか。
あんなにお酒を浴びても全く酩酊しない、そんな初めてで不思議な夜だった。
自分が葬儀において、人目を憚らず、慟哭したりする事が出来る人間なのだという事も初めて知った。
妹との思い出を一つ。
僕は良い兄貴では決してなかった。
年が近く、自分より非力の妹をいじめては悦に入っていたどうしようもない、愚兄だった。
小学生の頃だった。
たまたま、妹と2人で家で留守番をしていた時だった。
先程まで晴れ上がっていた空がにわかに曇り、そして真っ暗になった。
ぽつぽつと雨が降り出したかと思ったら、急に豪雨になり、そしてどこからか遠雷の音も聞こえだした。
僕はおもむろに近くにいた妹を抱き寄せ、膝の上に座らせた。
そしてしばらくそのままでいた。
そう、外が静かになり、母が勤めから帰ってくるまでずっと。
その日の寝る前に母に呼ばれた。
聞くと、妹がとても嬉しそうに母にこう言ったそうだ。
「外で雷が鳴って、不安になっている時に、僕が膝の上に優しく座らせてくれて、安心出来て、とても嬉しかった」と。
僕は珍しく母に褒められながら、心の中でそれはまるっきりあべこべなのにと思っていた。
不安で堪らなかったのは僕の方だったのだ。
妹の体温から伝わった膝の上のぬくもりが、僕の恐怖心をどれだけ和らげてくれた事か。
いつか妹と大人になってこの話を二人でして、笑い合いたかった。
そして、詫びたかった。
でももうそれは叶わない。
それでもこういう機会に彼女の事を思い出せる事は幸せだ。
それしか彼女にしてやれる事がないというのも少々情けないが。
僕の兄弟は他にもいるが、正直彼女の時程の激しい感情の振り幅が僕に訪れるか、疑問だ。
僕に出来る事は、妹が遺した幼い3人の子供達の未来を必ず明るいものにする事だ。
彼らには「お袋は早くに亡くなったけど、お袋の兄貴の変なおっちゃんが頑張って、僕らを大学まで行かしてくれた。お袋の子供に生まれて良かった」と思ってもらえるように。
それが僕の今後の人生のテーマの一つだ。
道半ばで亡くなった者の意思を継いで、まだまだ踏みとどまる事を許された僕はその思いを背負っていかなくてはならない。
本当は安らかに眠らないでほしいけど。
見守っていてほしい、我が愛妹よ。
JUGEMテーマ:日記・一般